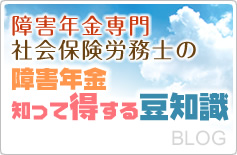8月 18 2025
障害厚生年金 多系統萎縮症 2級支給決定
難病の申請は、初診日の確定とか、初診日の病院に書類記載のお願いの際に説明が必要とか、申請準備の初めの段階から大変なことが多い。
しかし、この案件は異なりました。
初診日の病院で、既に「多系統萎縮症の疑い」と診断されていたので、スムースな申請準備ができた希少なケースでした。
大抵は、初期症状の「痺れ・足の上がりにくさ・ふらつき」などが出ても、現在の病名とは異なる検査を受けていることが多いです。
とはいえ、障害年金の申請上では、初期症状が出て、通院した病院が「初診日」となりますから。初期症状が出た病院で受けた治療や検査を記した書類作成が必要になります。この時、病院側に障害年金の申請で書類が必要な理由を説明しなくてはいけません。
ちなみに、病院に電話をすると当然ながら受付の方と話をすることになります。受付の方が、医師に書類の説明をしなくてはならないので詳細に聞かれることは仕方がないことです。また、病院からしたら、「なぜ、当院が書かなくてはならない?」と思われることは不思議なことでもなく、説明に時間をかけることもあります。その後、「医師に聞いてみます」とか医師が直接電話に出られて、質疑応答することがあります。
今回の案件の場合は、受付の方に簡単な説明で理解していただけ、直ぐに書類記載をしてもらえました。
次は、症状の確認です。実際の症状は、立ち上がりにくい・歩き難さや足が上がりにくい。などの起立・歩行障害が主でした。
どれくらいの症状か?は、面談の時に実際に見せてもらい、家出の生活ぶりを教えてもらえればわかります。
そして、医師に診断書を書いてもらうだけです。
問題は、診断書の肢体の症状判定です。
脳出血などの脳血管疾患とは異なり、筋力も関節可動域も健常と変わりません。日常生活能力の判定と医師が直筆する内容が、等級の要になります。
診断書の内容は、3級くらいか?と思いました。ですから、申立書の方で、とても詳細に生活ぶりなどを作成しました。
この診断書の内容だけでは難しい?と感じるときに、実際に面談で肢体の状態を見せてもらい、生活ぶりを教えてもらっていると精度の高い書類が完成します。
結果、障害厚生年金2級の支給が認められました。
「診断書が審査の全て」みたいに思われがちですが、申立書も審査書類であり、診断書の内容だけでは読み取れないことが審査官に伝われば、結果を左右することがある。という事例かと思います。
ここで難しいのは、診断書に全く書かれていないことを書いても、審査官に伝わらない。あくまでも、診断書に記載されていることの中から読み取れないことを書く。ということが肝心かと思っています。