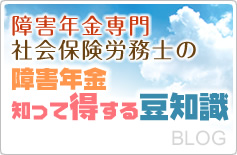障害年金 不服申し立て 中等度知的障害 1級認定
障害年金の結果に不服があれば、不服申立てができます。
ただし、不支給だったり、思惑通りの等級ではなかった。という理由だけでは、不服申立てはできますが、結果は変わりません。
結果が変わる確率は、3%とも5%とも言われているほどに低いです。
不服申立てをするケースとしては、診断書の内容から見て、得られた結果が明らかに異なるのでは。と感じた時です。
つまり、不服の理由が、診断書の内容の中にある場合しか、結果が変わる可能性はありません。
今回の案件は、障害年金の申請の結果、2級でした。
しかし、診断書の内容は、1級を示している。と、感じました。
また、ご本人の状態は、今後もこのまま変わることはないでしょう。ですから、「1級になるはずだ。しかし、2級なんだよな。」という結果は、今、不服申立てをして結果を変えておかないと、2級のままで変わらない可能性が高くなります。
だから、不服申立てをしました。
診断書の内容は、B型就労支援施設に通所しているが、指示通りにできない。ことが書かれていました。日常生活は、福祉サービスを受け、家族からの援助もあり常の援助を受けていることも書かれていました。
最初の結果は、ざっくり言えば「B型就労支援施設に通所できているから2級」という判断でした。
不服申立てでは、常の援助を受けているので、1級のはずだ。と、明示しました。その結果、1級が認められたわけです。
ご本人の状態が、これからも変わらないこと考えると、今回の不服申し立てで1級を認めてもらえたことは有意義な事でした。
ご家族等にこの結果をお知らせした時、大いに喜ばれていました。
本当に良かったです。ひと安心です。