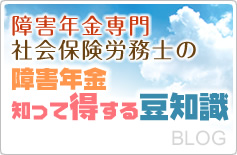10月 19 2023
障害年金 医師が「疼痛」の症状だけでは診断書が書けない。ということがあります。
障害年金の支給対象の症状に「疼痛」は、基本的には含まれていません。
しかし、「基本的には」というだけで、「特例」があります。
嚙み砕いていうと、その疼痛症状の「痛みの頻度・痛みの種類・痛みの継続時間」の3つを考慮の上、日常生活にどれだけ支障が出ているか?を判断し、支給か不支給かを審査する。という感じです。
つまり、痛みが弱く、服薬して痛みが和らぎ生活ができる程度ならば、支給されないことが可能性が高い。ということになります。
逆に、常に痛みがあり、「動かす度に強い痛みが発生」または「突然強い痛みが数時間おきに出現する」などで、生活行動を停止せざるを得なくなり支障が出ているならば、支給される可能性は出てきます。
痛みが強く生活ができないの中には、例えば、関節リウマチのように自分の足型に合わせた中敷きを入れなければ、屋内も屋外も歩行が難しい。というものも入ります。
このように「痛み」と言っても、人それぞれ生活に困っている場面が異なるので、一概に考えることができないのが「疼痛」です。
さて、診断書は医師に書いてもらわないといけません。ですから、治療を受けていないと、カルテはないし、診断書を書いてもらう事は出来ません。
治療を受けていても、痛みの原因が特定されない人がいます。
この場合が、「疼痛」のみで診断書を書いてもらえない人としては多いと感じています。
「痛み」の箇所・発生時期が一定ではない。痛みの箇所が日によって変わる。とか、痛みの発生時期が毎日ではない。とか、心理的な問題で痛みが発生している可能性を医師が考えている場合は、「診断書を書けない」と言われることが多いようです。
まず、心因的な身体の痛みは、障害年金の支給対象ではありません。
その他、医師が診断書をどう完成させたらいいか?解らないことも過去の依頼者様の例を振り返ると多いように感じます。
心因的な痛みではない。と医師が判断しているなら、診断書が必要であることを患者(依頼者様)が医師に説明・お願いすることで、医師が理解を示してくれて書いてもらえることはあります。
しかし、患者から伝えることで、医師の理解が変わる事は、医師の性格や判断によるので、必ずしも書いてもらえるというものではありません。
医師が書くことを嫌がっているのに、書いてもらう診断書の内容は、決して期待を超える内容にならないことが多いです。
医師も人ですから、心情があります。また医師の信条に反することは書けない。これらをお願いする方は、理解しておくことが大事です。